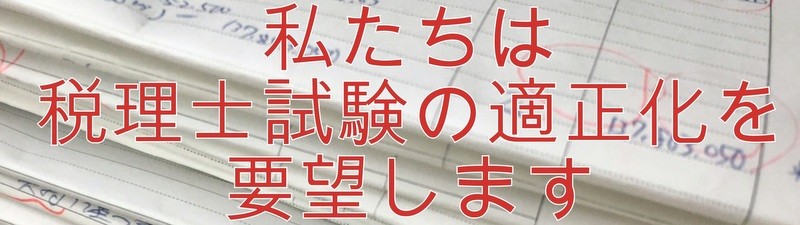判例評釈 最大判S60.3.27(大嶋訴訟、サラリーマン税金訴訟)「租税とは何か」
租税訴訟の中でも最も有名な部類に入る大嶋訴訟(大島と表記するものもあり)。ゼミで判例評釈を書きましたので、blogにも載せておきます。『租税判例百選』でも、一番最初に4ページとって金子宏教授が評釈を書いておられます。元はと言えば昭和39年分の所得税について争っていたものですが、最高裁で判決が出るまでに20年もかかっています。ゼミの教授に聞いたところによれば、当時はマスコミでとてもセンセーショナルに扱われ、ワイドショー的な番組で「サラリーマンの税金は不公平だ」と連日騒がれたそうです(その中には、自営業者は私的な出費を経費で使い放題という的外れな論調もあったようですが)。判決の中で「税金とは何ぞや」という根本が論じられておりますので、必見です。
目次
判例評釈
1 事実
1-1 事件番号・裁判の経緯
S55年(行ツ)第15号(大嶋訴訟、サラリーマン税金訴訟)最大判S60.3.27 民集39巻2号247頁、判時1149号30頁、判タ553号84頁
第一審:京都地判S49.5.30 行集25巻5号548頁
控訴審:大阪高判S54.11.7 行集30巻11号1827頁
1-2 概要
D大学の教授であるX(原告・控訴人・上告人)は、昭和39年に給与所得170万円余と雑収入5万円があったが、確定申告をしていなかった。所轄税務署長Y(被告・被控訴人・被上告人)は、Xに対して、総所得金額160万円余(うち、給与所得は、給与収入から13万5千円の給与所得控除を差し引いた157万円)、課税総所得金額114万円余、税額20万円余、納付すべき税額5万円余の決定処分と無申告加算税5700円の賦課決定処分を為した。Xは、これら処分の取り消しを求めて出訴した。
上告審係属中にXは死亡し、遺族が訴訟を承継した。
1-3 原告の主張
旧所得税法(昭和40年改正前の所得税法)における課税制度は、事業所得者等に比し、給与所得者を差別的に扱っているから、憲法14条1項に違反し無効。
① 事業所得等には必要経費の実額控除を認めているが、給与所得にはそれを認めず、これを著しく下回る額の給与所得控除を認めるにとどまるものであり、不公平である。(ただし、Xは超過の事実及び金額を立証していない。)
② 給与所得の捕捉率と事業所得等の捕捉率には大きな較差があり、給与所得者は著しく不利益な扱いを受けている。
③ 事業所得等には、合理的な理由のない各種の租税優遇措置が講じられており、そのため給与所得者は過重な所得税の負担を強いられている。
1-4 争点
旧所得税法における給与所得に対する課税制度が、憲法14条1項に違反し無効であるか否か。
1-5 参照条文
憲法14条1項(法の下の平等)
2 裁判所の判断
2-1 判決及び法廷意見
上告棄却。
原告主張①について
「旧所得税法は、事業所得等に係る必要経費については、事業所得者等が実際に要した金額による実額控除を認めているのに対し、給与所得については、必要経費の実額控除を認めず、代わりに同法所定額による概算控除を認めるものであり、必要経費の控除について事業所得者等と給与所得者とを区別するものとであるということができる。」と確認し、この区別が憲法14条に違反するものであるかについて、「国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないのである。(最高裁昭和25年(あ)第292号同年10月11日大法廷判決等参照)」とした。
「旧所得税法が必要経費の控除について事業所得者等と給与所得者との間に設けた前記の区別は、合理的なものであり、憲法14条1項の規定に違反するものではないというべきである。」
原告主張②について
「事業所得等の捕捉率が相当長期間にわたり給与所得の捕捉率を下回っていることは、本件記録上の資料から認められないではなく、租税公平主義の見地からその是正のための努力が必要であるといわなければならない。しかしながら、このような所得の捕捉の不均衡の問題は、原則的には、税務行政の適正な執行により是正されるべき性質のものであって、(略)租税法制そのものを違憲ならしめるものとはいえないから、捕捉率の較差の存在をもって本件課税規定が憲法14条1項の規定に違反するということはできない。」
原告主張③について
「仮に所論の租税優遇措置が合理性を欠くものであるとしても、そのことは、当該措置自体の有効性に影響を与えるものにすぎず、本件課税規定を違憲無効ならしめるものということはできない。」
2-2 伊藤正巳裁判官の補足意見
「租税法は、特に強い合憲性の推定を受け、基本的には、その定立について立法府の広範な裁量にゆだねられており、裁判所は立法府の判断を尊重することになるのであるが、そこには例外的な場合のあることを看過してはならない。」「特定の給与所得者について、その給与所得に係る必要経費(略)の額がその者の給与所得控除の額を著しく超過するという事情がみられる場合には、右給与所得者に対し本件課税規定を適用して右超過額を課税の対象とすることは、明らかに合理性を欠くものであ(る)」
2-3 谷口正孝裁判官の補足意見
「前述のごとく必要経費の額が給与所得控除の額を明らかに超える場合は、その超過部分については、もはや所得の観念を容れないものと考えるべきであつて、所得の存しないところに対し所得税を課する結果となるのであり、およそ所得税賦課の基本理念に反することになるからである。
そして、所得と観念し得ないものを対象として所得税を賦課徴収することは、それがいかに法律の規定をもつて定められ租税法律主義の形式をとるにせよ、そして、憲法一四条一項の規定に違反するところがないにせよ、違憲の疑いを免れないものと考える。
もつとも、本件において具体的に支出された必要経費の額が給与所得控除の額を超過するものと認められないことは、記録上明らかであるから、この問題は争点として取り上げるべきことではない。」
2-4 島谷六郎裁判官の補足意見
「本件の場合には、具体的に支出された必要経費の実額が旧所得税法所定の給与所得控除の額を超えるものと認められないことが、原判決の説示に徴して明らかである。」
「給与所得者にも必要経費の実額控除を認め、概算控除と実額控除のいずれかを任意に選び得るという選択制の採用の問題をも含めて、給与所得控除制度についての幅広い検討が期待されるところである。」
2-5 法廷意見の傍論的部分(租税の機能について)
「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付であるが、およそ民主主義国家にあつては、国家の維持及び活動に必要な経費は、主権者たる国民が共同の費用として代表者を通じて定めるところにより自ら負担すべきものであり、我が国の憲法も、かかる見地の下に、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを定め(三〇条)、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要としている(八四条)。」
「租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがつて、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。」
「給与所得者はその数が膨大であるため、各自の申告に基づき必要経費の額を個別的に認定して実額控除を行うこと、あるいは概算控除と選択的に右の実額控除を行うことは、技術的及び量的に相当の困難を招来し、ひいて租税徴収費用の増加を免れず、税務執行上少なからざる混乱を生ずることが懸念される。また、各自の主観的事情や立証技術の巧拙によつてかえつて租税負担の不公平をもたらすおそれもなしとしない。」
3 評釈
3-1 概要
結論としては終始主張が通らなかったのであるが、このような訴訟を提起し、給与所得の課税のあり方について議論を巻き起こしたところ、租税法に対する憲法判断の基準を示したところに、本訴訟の大きな意義があったと考える。金子宏教授も「租税法の判例の中で最も重要で興味ぶかい判例の1つである。」*1と述べている。
本件訴訟では、法廷意見、補足意見で触れられている通り、給与所得控除を上回る額の経費の立証ができなかったため、結論として敗訴することとなったが、それができていた場合には、別の結果も十分に想定されたと考えられる。
3-2 先例としての評価・影響
現行の給与所得に対する課税の仕組みも本判決当時と同じであるから、現行法の解釈についても先例としての重要な地位を占めている。
昭和60年代の抜本的税制改革において、給与所得の実額控除の代わりに、特定支出控除(所法57条の2)が設けられた。本判決において、給与所得控除制度についての検討が必要と複数の意見がついたことによる影響と思われる。
4 参考文献
- 金子宏「憲法と租税法−大島訴訟」『租税判例百選』(第6版)pp.4-7
教授の解説
- 租税公平主義を正面から扱ったおそらく唯一の判例。
- 大島教授は大学教授で経費がたくさんあっただろうから、きちんと立証していれば勝てていたのではないか。
- 原告主張②③は、原告の税金とは直接関係なく棄却されて止む無しというもの。法廷戦略としてあまり良くなかった。
- 谷口裁判官の指摘「所得控除以上に経費があるとすれば、所得のないところに対し所得税を課すことになり、所得税賦課の基本理念に反する」としているところが重要。
- 「租税法の定立については、……立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ない」=立法裁量論という。これを出されると基本的に税金裁判で納税者が勝てないという、やっかいな法理でもある。
*1: 金子宏「憲法と租税法−大島訴訟」『租税判例百選』(第6版)p.6